1. はじめに ― 採点基準は「ブラックボックス」
受験生にとって最大の関心ごとは「どう採点されるのか」。しかし実際の大学入試では、採点基準は原則として公開されません。だからこそ、断定的に「こう採点される」と語る先生や講師の言葉を鵜呑みにするのは危険です。
近年はそうした「断定型」の先生は減ってきているものの、依然として存在し、むしろ人気が出やすく信者化しやすい傾向にあります。とはいえ、本当に力を伸ばすには「採点者は何を評価するか」を冷静に考え、自分の答案をどう改善できるのかに意識を向ける必要があります。
特に出来る生徒ほど、「どう書けば点数が伸びるか」を具体的に検討することが重要です。基本的には模試で安定して点が取れることが大切ですが、模試の採点は比較的機械的であるため、「答案全体が論理的に成立しているか」という視点で信用できる人に丁寧に見てもらうことも欠かせません。
2. 具体例で見える“ズレ”
ここでは、私自身が経験した事例をもとに、模試と大学入試の採点の“ズレ”を紹介します。
東京大学の英語要約の採点基準
東大の第1問・要約問題には、大きくわけると極端な2つの指導スタイルがあります。
- 「本文のキーワードを徹底的に盛り込む」ことを重視する先生
- 「要約として筋が通ればよい」と考える先生
私が学生時代に受けた授業では、本文に明示されていないキーワードが採点基準にあるからそれを書けば満点だという指導がなされていました(今思うとさすがに極端)。
英語の採点の幅
英語を教えるようになって、かなり気になるのが和文英訳の指導方法です。
- 「心(意味)が伝わればよい」と指導する先生
- 「直訳でなければダメ」とする先生
模試では直訳が有利な場合が多い一方、大学入試は採点基準が非公開であるため、どちらが正しいと断定することはできません。意味を損なう意訳は危険です。これに関してはケースバイケースであり、その大学の問題の特性に合わせて指導することが求められると思います。幅広い解答が許容される可能性も十分にあります。
東京大学の社会論述の採点方式
私が学生時代、予備校の社会科論述の先生が「東大は4人で採点し、真ん中2人の平均点を取る」と話していました。真偽は不明ですが、複数人で採点して偏りをなくそうとする仕組みがあるのは確かです。つまり、記述問題の採点は人によって差が出やすいことを示しています。
世界史論述の経験
浪人していたとき、中世を扱う論述で、授業中に「この問題は“楕円の世界”で締めるとよい」と教わったことがありました。ところが別の予備校の模試で同じ問題が出題され、その表現を書いたところ、大きく減点されてました。田舎の学生だったので、予備校の先生のいうことがすべてだと信じ切っていたので、今思うとなかなかに、極端な指導だったなと思います。実際、東大で出題されたらどういう採点されたのかすごく興味があります。
現代文記述答案の解答
これは、みなさんも薄々感じている人もいると思いますが、現代文の記述問題って先生によって解答の出し方が全然違ったり、出てくる解答が別物だったりすることもあります。特に、東大や京大などの難関大学の問題ではよくあるように思います。つまり、絶対的に正しいひとつの解き方なんてあるわけがなく、いかに出題意図をくみ取って解答を作っていくか、それを教えてくれる先生に出会うかが大事なことのように思います。個人的には、大学の模範解答と採点基準は本当に興味があります。
3. 模試の採点基準は「多人数向け」
模試は全国から数万人が受験します。そのため一人ひとりの答案をじっくり検討するのではなく、あらかじめ細かい採点基準を設定して機械的に処理せざるをえません。つまり模試の採点は「公平さ」を優先し、本番の採点とは性格が異なると想像できます。
特に記述問題では、あらかじめ用意された「キーワード」が答案に含まれているかどうかが採点の中心となり、採点者はマニュアルに沿って一律に点をつけます。したがって、多少意味が通じる表現であっても、キーワードが欠けていたり、マニュアルにない言い回しで変な意訳したりすると減点されやすいのが実情です。
4. 難関大受験生へのアドバイス
だからこそ、難関大をめざすなら信用できる先生に答案を見てもらい、多角的なフィードバックを受けることが大切です。模試のように機械的な基準だけでは見えない部分――論理の流れや表現の自然さ、答案全体の説得力――を指摘してもらうことで、本番で評価される答案に近づけていくことができます。
その際に重要なのは、ただ「赤を入れてもらう」だけで満足しないことです。なぜその修正が必要なのかを理解し、自分の答案にどう応用できるかを考える姿勢が求められます。単なる添削の受け身ではなく、フィードバックをもとに自分の書き方を改善・再構成する作業を繰り返すことが、実力の伸びにつながります。
また、ある程度学力の高い学生は、先生の指摘は一人に限定せず、できれば複数の視点に触れるのが理想です。例えば自由英作文において、ネイティブの先生の採点と日本人の先生の採点では、評価が変わってくるとが多々あると思います。答案がさまざまな読み手にどう映るかを意識することはとても重要です。異なる観点からのコメントを受け取ることで、自分では気づけなかった弱点や改善点に出会えるはずです。
さらに、自分自身でも答案を客観的にチェックする習慣を持つと良いでしょう。例えば、書いた答案を数日おいて読み直すと、論理の飛躍や不自然な表現に自分で気づけることがあります。こうした「自己採点力」もまた、本番で安定した得点を得るための武器となります。

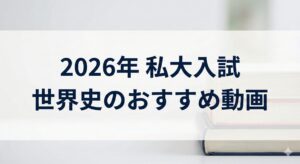
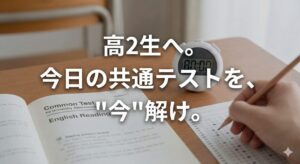
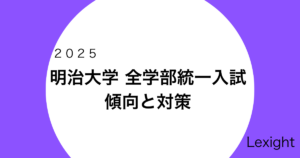
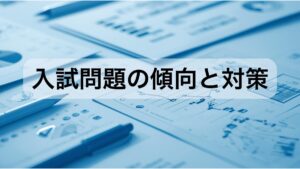
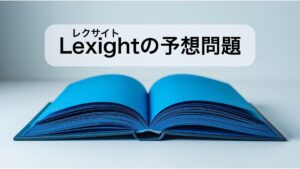



コメント