出題形式の概要
早稲田大学法学部の WRITING SECTION は、年度ごとに設定や題材が変化することで知られ、難度も高めです。特に第2問は、与えられた視覚資料から含意を読み取り、自分の見解を簡潔に英語で展開する力が要求されます。この設問に関しては内容が支離滅裂でも受かっている受験生が多くいるというのが個人的な感想です。
2023年
早稲田大学法学部の WRITING SECTION では、イラストや図表をもとにした自由英作文が出題されます。
2023年度からは出題数が1題から2題へ増加し、思考力や表現力だけでなく、実用的な場面での英語運用力も問われる形式に変わりました。
第1問《レストラン予約メール作成》
(2023年度出題)
友人の誕生日に合わせてレストランを予約するための英文メールを完成させる課題。件名・宛名・署名などは入力済みで、条件に従って本文を適切に書くことが求められました。
🎯 出題意図
この問題は、実用的な依頼メールを英語で丁寧かつ簡潔に書く力を問うものです。
- 構成の自然さ:目的 → 詳細 → 依頼 → 結びが流れるようにつながっているか
- 語調の適切さ:初対面の相手に対する丁寧で自然な表現になっているか
- 必要情報の網羅:人数・日時・目的などが過不足なく含まれているか
👉 実際の場面でも応用できる「実用英語」が求められています。
第2問《視点を逆転させた風刺画の考察》
(2023年度出題)
一羽の鶏が人間の赤ちゃんを小屋に連れて行く様子が描かれた風刺画を題材に、自分の考えを英語で述べる課題。
🎯 出題意図
この問題は、立場を逆転させた風刺的構図を通じて社会的・倫理的なテーマを考察する力を問うものです。
- 何を感じたか
→ I was confused at first, but then found the image thought-provoking.
(最初は戸惑ったが、よく見ると考えさせられる構図だった。) - どんな意味があると考えるか
→ It suggests how animals might see us if roles were reversed.
(もし立場が逆なら、動物から人間はどう見えるかを示唆している。) - どう捉えるか
→ I believe this image questions the ethics of how we treat animals.
(この絵は、私たちが動物をどう扱っているかという倫理を問いかけていると思う。)
👉 「単なる描写にとどまらず、自分の意見を展開する力」が重視されています。
2024年
早稲田大学法学部の WRITING SECTION では、イラストや写真をもとにした自由英作文が課されます。
2024年度も2題出題され、1問は「実用的な英文作成」、もう1問は「社会的・文化的テーマの考察」という構成でした。
第1問《空港までの列車案内》
(2024年度出題)
空港までの電車での行き方を説明する英文を完成させる課題。条件(列車名・時刻・乗換駅・特急券の要否)に従って案内文を書くことが求められました。
🎯 出題意図
この問題は、実用的な場面での情報伝達を英語で丁寧かつ的確に行う力を問うものです。
- 構成力:目的が明確で、順序立てて説明できているか
- 正確さ:地名・交通手段・時間などを過不足なく伝えているか
- 実用性:読み手が混乱しない、親切で自然な英文になっているか
👉 状況をふまえた「わかりやすい案内文」を書けるかが鍵でした。
第2問《ストリートアートの意味を考察》
(2024年度出題)
ストリートアーティスト・Banksyの作品「Cave Painting Removal」(2008年, London, Leake Street Tunnel)を題材に、「このアートがあなたにとって何を意味するか」を述べる課題。
🎯 出題意図
この問題は、与えられたイメージを出発点に、社会的・文化的な背景をふまえて自分の考えを表現する力を問うものです。
- 何を感じたか
→ I felt a sense of sadness when the artwork was being erased.
(そのアートが消されているのを見て、悲しさを感じた。) - どんな意味があるか
→ The man seems to be erasing not just the art, but also freedom of expression.
(作業員は単にアートだけでなく、表現の自由さえも消しているように見える。) - 自分の視点
→ I think this image shows how easily creative voices can be silenced in society.
(このイメージは、創造的な声が社会でいかに容易にかき消されるかを示していると思う。)
👉 単なる描写ではなく、「文化的・社会的含意を読み取り、自分の意見を英語で展開する力」が重視されました。
(出典:大学公表 / Banksy, Cave Painting Removal, 2008)
2025年
早稲田大学法学部の WRITING SECTION では、イラストやグラフをもとにした自由英作文が課されます。2025年度も2題出題され、1問は「実用的な依頼メール」、もう1問は「グラフとデータに基づく考察」という構成でした。ただし、第2問は2024年まで続いていたイラスト形式の出題ではなく、それより以前に出題されていたグラフの読み取り問題が出題されました。難度も高く戸惑った受験生が多かったことが予想されます。
第1問《課題提出延長のお願いメール作成》
(2025年度出題)
教授に課題提出の期限延長を依頼するメールを完成させる課題。件名・宛名・署名などは入力済みで、指定条件に基づいて本文を適切に書くことが求められました。
🎯 出題意図
この問題は、英語での実用的な依頼メールを、適切な文体・構成で書く力を問うものです。
- 構成の明確さ:挨拶 → 目的 → 理由 → 結びが自然につながっているか
- 文体の丁寧さ:教授宛メールとして適切な語調か
- 必要情報の網羅:指定された「目的」と「理由」を明確に伝えているか
- 実用的表現:件名・宛名・結語など、英語圏のメールマナーを踏まえているか
👉 短い中で「丁寧で簡潔な依頼メール」を正確に構築できるかが鍵でした。
第2問《アフリカに関するグラフの考察》
(2025年度出題)
国土面積と人口のグラフが提示され、アフリカの割合に注目して「そこから何が言えるか」を述べる課題。
🎯 出題意図
この問題は、視覚情報をもとに考察し、自分の意見を展開する力を問うものです。
- 気づき
→ Africa occupies a large portion of the world’s land, but has a relatively small share of the population.
(アフリカは世界の国土の大部分を占めるが、人口比率は比較的小さい。) - 社会的・経済的含意
→ This could mean Africa has great potential for future development and resource use.
(将来的な発展や資源活用の可能性を示している。) - 自分の視点
→ I believe the world should pay more attention to Africa’s growing importance in global issues.
(アフリカの重要性が高まる中、世界はもっと注目すべきだと思う。)
👉 データを描写するだけでなく、そこから社会的な含意を引き出し、自分の視点で論じる力が評価されます。2025年に第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)が横浜で開催されることから、この問題が出題されたのではないかと考えています。
解答の注意点
第1問(実用英語系:メール・案内)
フォーマットを守る
- 件名・宛名・署名は与えられている → 本文のみを完成させる。
- 「挨拶 → 本題(依頼・案内) → 理由・詳細 → 結び」の流れを意識する。
相手目線の丁寧表現
- 教授宛ならフォーマルに:
I would appreciate it if… / Could you possibly…など - 案内メールなら「相手が迷わない説明」を心がける。
必要情報の網羅
- 指定条件(人数・日時・交通手段など)を漏れなく含める。
- 情報を順序立てて整理し、読み手がすぐ理解できる構成に。
簡潔さと自然さ
- 語数は 必要最小限にとどめる
- 余計な表現を避け、シンプルでわかりやすい英文に。
第2問(考察型課題:グラフ・風刺画・アート)
描写+考察の二段構え
- まず「何が描かれているか/データが示すこと」を簡潔に説明。
- その後「そこから読み取れる意味」「自分の意見」を展開する。
論理展開の型を使う
- 気づき → 含意 → 自分の意見
- 例:This shows that… → This could mean… → I believe…など
社会的・文化的背景を踏まえる
- グラフなら経済・人口・環境の含意を考察。
- アートや風刺画なら自由・倫理・文化的象徴を読み取る。
一貫性と簡潔さ
- 語数は 80〜100 wordsが目安、
- 必ず「自分の意見・考察」を含める。
- 1パラグラフで論理を整理。
傾向まとめ
出題数は2題 が基本。
第1問=実用英語(メール・案内など)
第2問=考察型課題(グラフ・風刺画・アートなど)
👉 実用的な表現力と論理的思考力の双方をバランスよく評価する形式が定着している。
学習の仕方
1. 過去問演習で形式に慣れる
- 出題形式は 第1問=実用英語、第2問=考察型課題 と安定している。
- 過去問を解くときは「時間を計る → 書く → 語数を確認 → 模範解答と比較」を繰り返す。
2. 実用英語の対策
- メールの型を暗記:挨拶 → 本題 → 理由/詳細 → 結び の流れをテンプレ化。
- 定型表現をストック
- I would appreciate it if…(お願い表現)
- This is to inform you that…(案内文の導入)
- Could you possibly…?(丁寧な依頼)
- 演習法:授業や課題のシーンを想定して「依頼」「案内」「予約」などを英語で書く練習を日常的に行う。
3. 考察型課題の対策
- 視覚情報を言語化する訓練
- グラフ → 「最も目立つ特徴」+「比較」
- 絵や写真 → 「何が描かれているか」を簡潔に説明
- 論理展開の型を習得
- 気づき → 含意 → 自分の意見
- 例:This shows that… → This could mean… → I believe…
- 社会問題や文化的テーマに触れる
- 環境問題、人口動態、表現の自由など → 英語で意見を述べる練習をしておくと即応力が高まる。
4. 語数感覚と時間管理
- 80〜100 words を体に染み込ませる。
- 書く前に「要点を3つ程度」に絞り、100前後に収める練習。
- 制限時間を意識し、20~30分以内に書き上げる練習を積むと本番で安定する。
5.添削と自己修正
- 書いた答案は必ず「文法・語法の誤り」「構成の流れ」「語数」をチェック。
- 可能なら先生や友人に読んでもらい「伝わるかどうか」を確認。
まとめ
- 過去問演習が軸
- 実用英語(定型表現+構成)と考察型(描写+含意+意見)の両輪強化
- 語数感覚と時間管理を徹底
👉 この3点を押さえれば、どの年度の出題にも柔軟に対応できる。
今後の出題予測
第1問:実技系英語
これまで続いている 「実技の英語」形式(説明文や手順を英語で書かせるタイプ) は、2026年度も継続すると予想されます。大学側としても「読解+実用性」を試せる出題であり、定着する可能性が高いでしょう。
→ 今後の 新しい場面設定(例えば授業内での活動やプレゼン準備など)が加わる可能性も考えられます。
第2問:図表問題(イラスト → グラフへ)
2025年度で イラストからグラフ への転換が見られました。この流れは2026年度も続くと予想されます。
ただし、入試で使いやすいグラフ題材は限られているため、長期的にはバリエーション不足になるでしょう。
→ 少なくとも2026年度は グラフ型 が継続と見込まれる。
対策としては、2017年度以降の同学部・第6問のグラフ問題が有効です。やや古い題材ではあるものの、基本的な練習素材としては十分活用できます。
ただし、いわゆる 「政策提言型・意見提示型」問題(社会的テーマに対して自分の立場を英語で述べるもの)が出題される可能性も残されています。これまで自由英作文で頻出してきたオーソドックスな形式であり、突然の復活も想定しておくべきでしょう。
→ 「環境」「教育」「経済」などの定番テーマに備えて、論理展開と語彙のストックを意識した対策が必要です。
参考・推奨教材
- Lexight刊「難関大学への自由英作文【現代日本の問題編】」
- 関連記事リンク

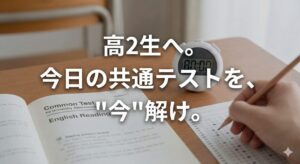

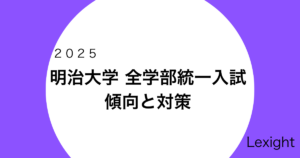
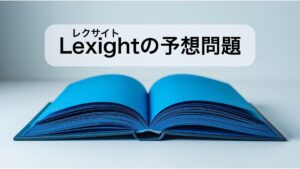


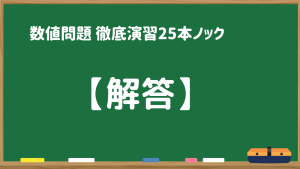

コメント